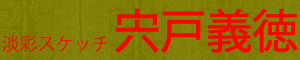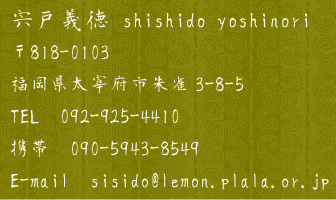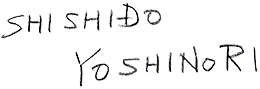| 詩集 ちょっと違うだけで |
| 宍戸 節子 |
| 目 次 * * |
| 湯葉 乳の熱を上げていくと 表面に湯葉が張る はしゃいだとき テンションを高くしたとき 自分を見詰める膜ができる 醒めながら いつものわたしに戻りながら はしゃいでいた自分がみえてしまう ずれていた会話 あなたを 掴んでいなかったことがすけてきて 切なさが回りだす まわりながら 突いてくる あなたと暮らしていると 合わない部分が 寂しげな膜になる 心は 掬い上げたばかりの湯葉のように 頼りなげに震える |
| 戻る |
| たか菜漬け あなたの体をわたしの左手で支える わたしを支えているのはあなたの右手 互いに支え合ったたか菜の葉と葉 筒の形をした葉に塩を振る わたしだけの膜に 塩が浸み 掴んでいるわたしが少しずつ溶けて 出ていく ゆるんだ細胞膜をくぐって あなたのそばへゆく 溶け合ったわたしたち を 乳酸菌が食う 食われて味わいを深める あたしであるあなた あなたでもあるわたしたちは しわしわになりながら 違った味の旨さとなった ことばが沁みる こんなことがよくある 「なんば いよっと」 あなたから強く吐き出されたことば わたしもこんな風に強くいったことがある ことばにおされ
しわしわになりながら 漬かっていると 違ったわたしが匂ってきた
あなたの気持ちを 広がったわたしに 染み込ませ 音を聴くように あなたの心を鼻の奥に響かせて いく |
| 戻る |
| さわし柿
ひいばぁちゃんは果物屋で 練り柿を売っていた 風呂桶の湯に一晩漬けて 渋を抜いた甘い柿 いまでは 炭酸ガスやドライアイスの ガスさわし アルコールや焼酎を噴霧する アルコールさわしになった さわすとは 糖からアセトアルデヒドや エタノールを作ること 渋い水溶性のタンニンを これらの力をかりて ペクチン質にくっつける 溶け出さないように だれもいない家に帰ったとき 底しれぬ静かさを感じることがある 寂しさが水溶性となって沁みてきて だれかと話さずにはいられない 電話帳を繰り だれかれとなく電話する さっきの友人の電話も 心をさわすためだったのだろ |
| 戻る |
| アイスクリーム
アイスクリームには等量の空気が含まれる 氷と気泡が細かい粒となって 未凍結のアイスクリームに混ざり込んでいる こまやかさがなければ ことばは心を開けない 湿りがなければ ことばはあなたに馴染めない 甘さがなければ あなたのなかにはとどまれない あなたの意固地になっていない部分に わたしのやり方を投げ込む わたしの心地よさが泡になって混じる あの人の嫌がることもあの人に沁みていき 「そんなことして なんになる」 なんてことはいわなくなる
あの人のなかに わたしが 半分程混じり あなたを柔らかくしている 泡のわたし |
| 戻る |
| 牛乳
わたしもあなたも 水溶性の膜をかぶり 世間に馴染みながら 白く小さくなって浮いていた ある日 隣の乳脂肪に 「お出かけ?」って 声をかけたら 「ちょっと」 とさりげなく言葉も心もかわされた 水に馴染むための膜もなんだか 互いに距離を作ってしまうものだ わたしもあなたも孤独な玉となって浮いていた 寂しかったわたしは手を伸ばし泳ぎだす 「今夜からわたし くりーむになるからね。 水を除けながら ひとに近づきながら」 「牛乳のままではだめか」 「泡立つ くりーむなの。 ほいっぷ くりーむのように ふっとぶ くりーむ」 「ぜいたくな」 「夜 小説の講座にいくけん」 「ひとりで飯くうのか おれ」 「洗濯物も取り込んどいて」 「おれが」 これがバター作りのチャーニングなのか 壜のなかでわたしとあなたの掴んでは脱ぎ捨てた 水の塊が渦巻いた 「僕の価値観が壊されるー」 あなたの息つかいが叫びになったとき 壊しているんじゃないの あなたらしさを作っているんだといってやった わたしの膜があなたに食い込み ふたつの膜が削げた ぶつかるたびにわたしたちは透けていった チャーニングがおわったふたりの膜はぼろぼろで 剥き出しの乳脂肪は絡み合い 涙と汗の塩気を付けて固まった |
| 戻る |
| パン
あなたとわたし 話すほどに伸びるものがある 暮らすほどに絡むものがある こねあってふたりは粘りも増してきた そこに イースト菌が 甘さを アルコールと炭酸ガスに変えていく 思い出の部屋のひとつずつが膨らみ アルコールの香りがふたりを酔わせる 膨らんだものは日々の思い出 暮らしのなかでつちかった思いやり ふたりのなかで育てた自己主張 オーブンで焼くと 網目の部屋には つかみ取った甘味と 少しばかりの愛が とりこめた その後は生きたなごりの穴と香りを 人生の味と思い もう膨らむことのないパンを ふたりでじっくりと食う |
| 戻る |
| 豆腐のにがりと凝固剤 あなたのことばが心の窪みに届く うるおいが染みて わたしを包んでいたものが 内側から溶ける 外皮も潤び 柔らかくなった大豆 あなたの ことばのひびきが臼の幅で揺れるので わたしだけの固まりが細かく擂れていく 向けられた視線が強いほど 眼差しが温かいほどに 受け入れられるわたしは 温められ いくつもの襞から 沢山のわたしが溶けていく どれだけ溶け出したのだろう わたし おからと離されたあとは 羽ばたきと息つかいを苦い海水で固め 甘い香りのにがり豆腐となった 聞き耳を立ててくれなかった日の豆乳は薄く チューブに えぐいグルコノラクトンの凝固剤と共に容れ 甘味の薄い袋豆腐になる 普通の幸せは硫酸カルシュウムで固めた 絞り出せただろうか 襞の裏側まで食い込んだものを どれだけのものが解け合えたのだろう わたしとあなたの温めあいのなかで 出し切れたのだろうか 襞の内側のどろどろの思いと希望は 濃い豆乳は命のもとになる 海の水からとったにがりをうって 日々を甘いものに変えていく |
| 戻る |
| 糠床 手を入れかき回し 周をたどって辿って輪をえがき たたいてたたいて ぬかどこは捏ねつづけられ 香りは重なり合ってつくられる 生まれ落ちた瓶のなかは かあさんとばあさまの味がした ぬかみそのなかで かあさんがお辞儀しばあさまが正座する 重なる手と手と私の手 捏ねつづける手のひらから 香りつづけるものを掴みとる 香りに満たされながら たたいてたたいて 私の香りをたたき込む |
| 戻る |
| ソーセージ
食塩があると、たんぱく質は溶け出し糊状となる。 本来混ざり合わない水と油を、糊状のたんぱく質は あたかも乳化したように練りあげる。 熱すると、脂肪球を囲みながらたんぱく質は凝固する。 脂肪は溶出しないで、保水性の高いソーセージとなる。 弟と妹が近くに感じられないときがある 違いばかりが気になって そんなとき母から電話があった 「宏がくるけん」 母の家で会うとまた 弟が近くなる 性格の違う三人の子供と 母はうまく付き合ってくれる 母は弟の家へ泊まりにいく 妹は母の検診に付いていった わたしはおかずを持っていく ホルマリン臭いので無垢板で食料入れをつくったよ 私の食糧庫を見て母は 「よかね。ほんものの木は」 次の日妹の家に行った母は ホルマリン臭い合板の食糧庫をみながらいっていた 「使いやすかろう こんだけ入るなら」 食糧庫を作らなかった弟にはこういっている 「いらん いらん 食糧庫なんて いるときは買いに走ればよかもん」 |
| 戻る |
| ポテトチップス
揚げるとは 水分を油と置き換えること ポテトのなかの甘えを油のなかに捨てること 親から植え付けられた曇り 自分で付けてしまった慣れをとかすこと もってしまったために傷ついたプライドを 油に吐き出し 起立するサックサクのポテトチップス 自分らしく生きていけるようになったのは 三十歳を過ぎたころだろうか 「夜に映画にでかけるなんて」 こう母がいっても出かけられるようになったのは 「出かけてばっかりおらんで、家ば片付けんね」 つれあいにいわれても 家が散らかっていても 行きたいところにはいつでも行けるようになったのは 胸を張っていたいのに すぐに 空中の水分でしなしなになってしまう 「僕の絵の仲間に近づきたいために絵を描くのだったらやめてくれん」 思ってもいなかったつれあいのことばで 立ち上がれなくなる やっとの思いで やりたいことを見つけ 水気を吐き続けているのに 湿気が入らぬように 口をしっかりくくるのに ときどき どかっと 水分に襲われる 手も足もぷるぷるになりそうな日々のなか ちょっとしたプライドをささえにして もう一度胸を張ってみた |
| 戻る |
| たくあん 母におぶわれていた頃 「かわいいね」っていわれると 「アパン嫌」といって 反対を向いたわたし アパンとはおせじのことだったのか おせじは嫌だけど きちんとわたしに向き合ってもらえるならば わたしのことばが発酵できるほどに受けてくれるならば 納得したことだけやりたいわたし でもどこかでだれかに合わせている 本当の自分はなんでも納得していたいのに 人と合わせてばかりいると 本当の自分がぽょよん ひょっこと顔を出したがる ひっこんでいなさいといっても 自分のこと半分は出させておいてという 干され 沁みだされ たたかれ 変化させられた私のにおい それでも 生だいこんのにおいを持ちつづけていないと たくあんにはなれない たくあんのにおいに向って やりたいこと引っ提げ すてっぷ踏んで いく |
| 戻る |
| ほぐす ほぐさない飯粒は 釜の型のままに固まる ほぐせない飯粒も 釜の型のまま固まった 飯粒は 湯気のなかでほぐされる あたたかさのなかで ひと粒ひと粒をつぶさぬ思い遣りのなかで ひと粒の重さのなかで ほぐされる 心地よさ ほぐす 心地よさ 柔らかさにふれた飯粒は 出会いのあたたかさに囲まれ 湯気くらいの思い遣りで ひと粒の白さと重さを もとめあう |
| 戻る |
| ヨーグルト
カゼインから プラスとマイナスの電荷が 溶け出してくる つりあってゼロになっている牛乳の 乳糖を乳酸に変える 乳酸菌 乳酸が増えると カゼインは酸性になる 少しずつ少し少しと酸が増えて カゼインは等電点になる 等電点にたっすると 乳たんぱく質カゼインは 等電点沈殿をおこし 牛乳は固形物(カード)となる 「またパンの袋ば あけたままにして カチカチになっとうよ」 「部屋出るときゃ 暖房ば 消してよ」 「こげんか所(とこ)に 靴下ば 置かんでよ」 口を開けるたびに ふたりのなかに 乳酸が増えていく マイナスへと傾く電荷を 我慢と寛容でプラスへと戻していた心が 等電点になったとき つれあいは固くかたまって カードになった |
| 戻る |
| 圧搾と抽出の油
山での暮らしは 圧搾で絞る油のようだ 人間らしさをじんわりと絞り出す 壊れやすく 崩れそうな声を守る 村人がいてくれるので せかされたり 振る舞いを変えることもなく ことばを目立たせることもなく 暮らしていけた 大分にある安心院の山の上で育ったつれあいは 町にある小学校での入学式の日 人声の多さで体が震えた 母親に「義ちゃんふるえんとき」 そういわれてもふるえがとまらんかった 町は 抽出の油のようにすべての欲望を溶かし出す 油を抽出するベンゼンは 眠っていた声までも溶かしてしまう 見知らぬ人がいるなかには 人は ねっとりした思いさえも 適えられるものとして吐き出すのだろう ベンゼンに溶け出たガム質が おっとりとしゃべる声を固めるので イオン交換樹脂と活性炭で取ってもらう と もったりしゃべっていても 聞き耳を立ててくれていた耳の ビタミンEまで取られてしまった おっとりと話すので聞いてもらえないまま つれあいは ビタミンEに守られた 霧の上の村から 山道を下り 小学校へ向って 毎朝 抽出の油のように 多くの声が融けた 霧のなか に 入っていった |
| 戻る |
| コンニャク
姑は言った あんたは 私をほっといてくれるけん 親孝行じゃ 依頼心は強いが 独立心も強い姑は 世間の生き方に 私に べったりべたべたと貼り付く糊のような 粘度の高いものは求めなかった 九十六歳までひとりで暮らし 好きな時代劇を観たくなると 「あんたたっちぁは もう帰りなーい」 こう言ってすぐ ひとりになりたがった
糊状のコンニャクも 藁灰や石灰のような アルカリに出会うと 網目構造を形成する 足が浮腫んだときは抱えるようにして 前の道を何度も何度も歩かせた 手芸が好きで話好きな姑が喜ぶ 養護老人ホームも懸命に探した 自分のしたいこともできて 姑も幸せになれる 網目構造をつくるために 動いたら 私も姑も もちもちっとした コンニャクになって きた |
| 戻る |
仲を切ろうと右にもがいても 左に強く振り切っても どこまでも いつまでも細くなってでも付いてくる 糸 好きなんだから とか心配だから と言っては 思いやりの糸を吐く あの人 ひとりよりよかたいと あの日から支え合い暮らしてみた あの人の吐く L型 グルタミン酸とフラクトースを 旨い甘いと 味わっていると 甘さが染み込んだ ことばの端々には 一万個ものD型のグルタミン酸が繋がっていた D型のグルタミン酸は旨くもなく 骨粗鬆症の姑は一日中 「あいたった あっ痛った」と唱えている D型のグルタミン酸の糸は 甘さを無くしてしまった フラクタンと絡み合い 高分子吸収体になっていく そんな糸に わたしも取り囲まれたのか 遊びに行っても呼び戻され 姑が熱をだしたと手繰られて 自分の旨みを味わう暇もなく あの人の吐く旨みを しずかに受け取る暇もなく 旨みを深くする L型 グルタミン酸から 強い繊維にもなる D型 グルタミン酸へ 心の構造が変っていく |
| 戻る |
| かまぼこ ずっと この曲がかけられなかった これを聴くと 挨拶をしなかったために 寂しく帰ったという 舅を思い出した 三十年も前のこと 舅は夫と話していたので 私は遊びにきていた友人と リストの「愛の夢」を聴いていた 「なぜ 挨拶しなかったの」 皆が帰った後に 夫からいわれた 「おやじが もう帰るってよ」 こう 声をかけてくれればよかったのに それだけで 舅も私も傷つかなかった それからの日々 舅とのふれあいのなか 少しずつ 塩をふり 寂しさを沁み出させ 擂り潰した 笑いのなかで 舅と夫の ふとした 心の揺れまでくすぐってくれる会話は ほどよい塩味で届いたことばは あたらしい私をつくってくれた 「愛の夢」が聴けるようになったころ みっつの心も蒸しあがった 歯ごたえのあるかまぼこは 旨い味がする 噛みごたえのあるかまぼこの 新しい結合
* すり身に塩を加えたら、 ミオシンとアクチンが溶けて 新しい結合を始めた。 熱を加えると 結合は確かなものとなり、 足の強い歯ごたえのある かまぼことなる。 |
| 戻る |
| ドーナツの穴
わたし 毎日 家族と 同じ色になって ちいさなドーナツを回した わたしもドーナツの上で 日ごと年ごとに心をよぎる色 の独楽を回したいのに 朝な夕なと求める声に追われて 穴の中で フライパンばかりを回していた ある日 わたしの色が ドーナツのうえには見えないとあの人がいう それに時々ドーナツの穴から 嘆きの歌が聞こえるらしい そんなに穴の中にばかりいては 自分の色を出せないよという 持ち色のチューブを出し尽くすこと それが生ききるってことさと囁く そういえばわたしのおっぱいの下あたりで 蓋をあけない色のチューブが 干からびそうになっている 融けなくなる前にと急いで色を取り出すと 家族も飯々と叫ぶ代わりに フライパンを回し始めた ドーナツの上に自分色の独楽を回したとき ドーナツの穴は消え 家族はまぁるいパンになった |
| 戻る |
| 消し炭 祖父も祖母もいなくなった家に 消し壷がある。 人の頭部のような 素焼きの壷だ。 祖母は飯を炊きおわると 熾きになった焚きもの を この壷に蓄えた。羽釜から吹きこぼれそうに 大きな湯気が立つと 分厚い木の蓋を少しずらし 焚きものを 手前に引いた。 炎が出なくなると 火消しん棒で摘まみ 消し壷 にしまった。 十年前から残されたままになっていた 消し壷の 蓋をあける。艶のある 黒い消し炭。 一度消えて もう一度燃える 消し炭は 出会っ たころの 祖母の髪。 祖母の語ったことばの刻みが残る。 藁に 火い 付けて 焚きもん に 火ば 移さんば とよ 火吹き竹がある。筒のなかをみていると カマド に顔を寄せ 火吹き竹を吹くときに 祖母が鳴ら した ヒィゥウーという 音が聞こえた。焚き付 けのとき尻を乗せていた 木切れも カマドの前 に 転がっている。 |
| 戻る |
| 母 「あの人 くさん 佐賀弁のひどかね」佐賀弁まるだしでしゃ べる人に会うと母は言う。自分は佐賀弁まるだしではない つもりらしい。 「今日来た植木屋さんくさん すかんとよ 私が ひとことふ たことしきゃ 話さんとに 『奥さんな佐賀でっしゃろう』って 言んしゃるとよ」 母のことばには 故郷の懐かしさがある。恥ずかしいという 意味の〈ちゃあがつか〉ってことばを聞くと「はずかしか」と 言うよりも もっと恥ずかしい気分になる。 母は六人姉弟の四番目 男が大事にされていた時代の三女。 家のなかでもどこにいるのかわからない存在だった。女学校 を出てからは同級生たちと近くの郵便局に勤めた。そのころ よく電報を打ちにくる男がいた。男は 同僚の間で一番の 笑いものだった 「あのずんだれくさん また ふられた ごたるよ」 一番口の悪い同僚が言うと 人のよさそうな同僚まで 「やっぱり あの顔と あの風采ではね」と相槌を打つ。 母も「なんか 田舎くさか 人やね」と思っていた。 その男がある日 知り合いに連れられて母の家へ来た。 知り合いは言った 「ほら ねえちゃんと妹と どっちでん よかけん 気に 入 った方ば もらわんね」 男は「妹の方がよか」と答えた。 母は嫌と言えず 押し入れに隠れていた。 見えないようにしていれば 話はなかったものになるよう な気がした。 客が帰ると父母と兄から告げられた 「あん人なら浮気もせんじゃろうし 学校出やから生活の 心配もなかたい あん人と結婚せんなら 家ば出ていけ」 泣く泣く母は結婚した。 父と母は日増しに仲良くなった。互いのいいところだけ見 るようにしているという。真面目で人の良い父は 三味線 や俳画を楽しんでいる母に 「おまえは いつも がんばるのう」と声をかけている。 私は父の口臭とか腋の臭いがいつも気になっていた。 なのにある日 母が言った 「とうちゃんな よか ところも あるとよ。体臭の ひ どか人が 多か ばってん とうちゃんな なぁーんも 臭う なか もん ね」 |
| 戻る |
| これくらい 病室に入った私を見た父は 白内障で白っぽくなった目で 時計の針の指し示した 四の数を確かめて なにかいった。 近づけた私 の 耳に 父のことばは 音として 伝わった。 父はもう一度 同じに響く リズムの固まりを 繰り返した。 音を送りだす 父の 口もとを 見る。それでも 音の中身を 取り出せない。 「もじゃもじゃもじゃね」 日常のリズムのなかに込められた 父の感情が かすめる。 父のことばが理解できた のは ことばの滴が 六度目に 私の皮膚に 染みた ときだった。 「なんで もっと 早く きてくれなかったの」といったのだった。 やっと理解してもらえて 父はにこっと笑った。 心の反射が届くのに 遠い距離があった。 腹の 上に おこうとして 左手で マヒした右手を 持ち上げる。 手を添える。ひんやりとして 鉄(かね)のよう。並んだ骨が 浮 き出ている。きょうも 点滴の針が 乾いた皮膚に 刺さっている。 針のすぐ上の 黒い紫色のにじみは きのうの針跡。 父は 子どもたちが小さかったとき いつも この 手で きいた 「とうちゃんと かあちゃんと どっちが 好いとうか」 「かあちゃんは こんくさいか」 私の目を覗き込む 父の 手をみると がっちりした手の ひらを 肩幅くらい広げていた。 私が「もう ちょっと」 と いうと 「じゃあ とうちゃんは どんくさいか」と いい 母への愛より 多い量を示すまで「もっと好いとろ うもん とうちゃんのこと」といった。 父が昔いったことがある。 「かあちゃんは おれのことを しんからは 好いとらん けん とうちゃんはさみしか」 父は 自分の寂しさを わかってくれない人と 暮らした のだろうか 愛している 妻なのに 尽くしてくれる 女 なのに 溶け合った アイスクリーム の ようには ひ とつに解け合えない ものを 感じていたのだろう 「とうちゃんのこと どんだけ 好いとう か」 父が 尋ねる この ことばは ただの じゃれごとだと 思っていたが このごろになって しっかり愛してくれと いう 父の叫びに思えてきた。 |
| 戻る |
| 祭りの綿菓子 闇の時間の迫るたそがれどき、祭りにでかけた。うっすらと暮れかかるなか 店先にほんわりと綿菓子は灯っていた。明かりのなかの綿菓子は、私たちの もとに神さまのやってくるときの目じるし。綿菓子を持って参道を歩く。 神輿をうごかすように 押し車押す おばあさんと社に向かう。おばあちゃ ん の神輿がうごく。しゃり しゃりしゃり。押しながら おばあちゃんの 神輿につぶやく おばあさん。 「東京にいる息子がのう、一緒に住もうというんじゃよ。そいばってん、私 しゃ、今までと同じんごつ、畑で好きな野菜ば作っていたかもんのう」 「ひとりでは心細くはなかですか」 「おとしゃんの生きとらすときも、じいちゃんやら、ばあちゃんのいいなり で、私しゃいつもひとりじゃった。若いときは、みんなの目のおとろしゅう て 腰も延ばせんじゃった。そいで ほれ こげんに 腰の曲がったんじゃ よ。もう 人の目を気にして暮らすとはきつか」 祭りの翌朝 綿菓子は溶けて流れていた。 叫ぼうとして 押し停めた人の声 わかってもらえない嫁や姑のためいき。 綿菓子は よみがえるために振り捨てたはかない望みを受け止めたのだろう か。生きていく ときの辛さを知ったのだろうか。 ふんわりしていた綿菓子は 祭りに集まった人の苦しさを溶かすために一晩 中泣いたのだろう。 溶けて流れたものは 伝わることのなかった ことば。 |
| 戻る |
| 祭り(献り)の綿菓子 翌朝 祭りの綿菓子は 氷結の涙となっていた 流れのまま固まった 人の声 殉ぜずふりすてたいのちの いまわたち ゆんべ 魂ふり漂浪(さる)き 見ること忘れ ひとり駆け出し灯へ向かい 祭りに取り付けた 生き死のあわい まぼろしの舟に灯った綿菓子を 舳先へ差した祭りは 一夜の夢 道行きの綿菓子は えにしの旨味(しみ)があると 祭りの後は いつでも いのちの固まりを 食っている |
| 戻る |
| 恋 軒先で鳴く声はクォォーッ クォォーッ クォォー しだいにせつなげになる。 鳩の声は先程まではのびやかだった。クック ッー クークッコウ 空いちめんに晒される 反物が クックッー と流れていくのを クークッコウで ぐいと自分のもとへ引き寄 せる アクセントのある鳴き方だった。 晒される反物の気分で のどかな休日の朝 鳩の縄張り宣言を聞いていた。 しかし今鳴いている妻を恋い求める声は細か い振動で心の深奥を引っ掻く。 薄皮でやっと包んだ人恋しさが 揺すられな がら剥ける 銀杏のように その色を見せる。 大学院へ行くために夫と別れて住んでいた夕 暮れどきなど 恋しくて 夫の住む町に向か って 名を呼んだ。共に暮らせるようになり 恋う心を薄皮で包んでいた。今鳴きつづける 雄鳩のときめきは 家を共鳴させ 心ふるわ す揺れのなか 夫を恋するくらいではありあ まるほどに 男を恋したい気分になる。 もう寝てはいられない 外を見た。隣の屋根 に二羽の雌鳩 この鳩たちも 雄鳩の クォ ォーッ クォォーッ と呼ぶ声に 身も心も 捕らわれてやって来たのだろう。雄鳩の呼び かけは切羽詰まってきた 私も夫が恋しいと 叫びたいのに 彼は鳩の声も気にせず のん びりと横で寝ている。この男も結婚前は毎日 電話かけてきて この鳩のように せつなげ な声をなげかけていた 夫のくちびるに手を。 そのときだった 一羽が軒先の愛の巣へ入っ た 頭の上で カサカサと二羽の歩く足音が する それから音は止んだ 心乱す声はおさ まった。それでも鳩が気になり 起き上がれ ない 鳩たちの下で本を読む 鳩と同じ静寂 のなかにいる。 昼になっても 軒先からの音はない 窓をあ けると 音に驚いた鳩が隣の屋根に飛んでい った。 二羽は屋根の端と端にいて キョトンとした 目でこちらをみている。異性を求める人のよ うに トロリとした目ではなかった 子供の ようにさわやかな目である。 しばらく静かにしていたら 仲良く軒先の巣 に戻った。静かな時が また 続いた。 |
| 戻る |
| 春の海 内へ内へと響いていたカモメの声も ギィァ ギァィーとバウンドしながら波と同じ方向へ 流れていった。 のノ字に身を縮めていた私は 海からの風に あったかさを感じ 少しずつ体を緩ませ 両 手を広げて ひノ字になって 砂の上を歩く。 波打ち際から遠い 波跡の上 重いホンダワ ラが残されている。 大潮の日 満ち潮に乗ってやってきた 藻は 戻る波の力で は 帰ることはできなかった。 隣の波跡は海草の花畑である。褐色の藻の上 に 軽い紅と緑の藻がつくった 波の形した 重なりは 波と平行にどこまでも続いている。 アオサで緑に見える波は ザッ.ジャワンと 五連符を弾きにやってくる。浜の鍵盤をまず 右手で弾く。左手は次々にやってくる波に押 されてもう 小指から ウウィウン と音を 出した。 弾きおえて手を戻すと 隣の右手はもうジジ ジジ 音を出している。返るとき波はウッフ ン ため息を漏らした。ザッ.ジャワン.ウ ウィウゥ.ギシン 押し合う水は 音を生む。 ジャジャ.ザウザウ.ウッウ.ウッザー ジ ィザー.トポン.ジャジャー.ジャワジャワ 波は 絶え間のない 音と おとの 重なり。 |
| 戻る |
| 日の入り
私と太陽の間に 道ができた。正面にできた 肩幅ほどの道は 水平線から私の足元まで続 いている。 内海の穏やかな水面に 波の数だけ丸い太陽 が並び それがひとつの線となり 右と左には楕円の太陽も連なって これはま るで海から生まれた背骨である。背骨はもう 一本 光が水に透過するために 海の底にも 伸びている。 太陽は私の目の高さにあり 私と足元の赤い 道と太陽は 三角形で結ばれた。 地球上の北から南まで 同じ経度の上にいる 何億もの人が今 西を向いて この三角形で 太陽と結ばれた。 太陽は今 はるか遠くから あぶくよりも小 さな地球を照らしている。地球の刺のように 小さな私が 地表すれすれからみているので 目線よりも低いところにある水平線は 手が 届きそう。水平線のすぐ上の太陽も こんな にも近い。 太陽は輝きを重ねた赤色のなかで 燃え尽き る線香花火のように 力みの発火をする。 東にそびえるあの山の向こうで日暮れを迎え させた太陽が 今 水平線に沈んでいく。 太陽が半分隠れると 膨らましたゴム風船か ら ひと息分の空気を抜き取ったように 空 はぬにょうと音をたてて ひと吐き分だけ色 を濃くした。空気も一掴み分だけひんやりと なり 音と光を吸って 木琴のような分厚い 板になった。 太陽から延びた 背骨の形をしていた 道は もう まばらになりながら 揺れて いる。 |
| 戻る |
| 夏の海 太陽からの光は 鉄琴のように細かに振える 空気のなかで もも色のゆらぎとなっている。 波は空の色を写しながら揺れるので 海は水 面でコスモス色のゆれを返した。 浜辺にできた わずかな砂の盛り上がりの線。 潮が満ちてくるその勢いで運ばれた粗い砂は 少しずつ引いてゆく潮ではもう運べなかった。 波は引くとき砂地の中の水を連れていく。砂 地からじゅわぁんと 水が引くと 生まれた ての赤子のような肌 が水際にできた。柔ら かな砂は 素足になった指のすきまをくすぐ りながら抜けていく。 湿った砂の上にも さくら色のゆらぎと 銀 の粉を流したような空の色が うっすら映っ ている。 しっとりとした砂のうえには ひと波ごとに 海近くへと退いていく 月と波の戯れが 一 本の線となり 大地の皺のように 同じ幅で 並んでいる。 |
| 戻る |
| 雨の音 都会で暮らす男がある日 雨が落ちるときの音を聞きたいと思った 彼は山の中で暮らし 鶏を飼うことを生業とした 茅葺きの家を建て 落ちる雨を聞いた しかし 茅ではじける雨の音は 雨と茅がぶつかる音で 雨が落ちるときの音ではなかった 雨が落ちるときの音が聞きたい彼は 卵を抱き温める鶏の横で 落ちる雨を聞いた 雨が藁葺きの上にじんわりと落ちるとき 男には雨の落ちた音が聞こえた |
| 戻る |
| 歌垣の故郷 私が育ったのは 佐賀県杵島郡大町。昔歌垣が行われていた杵島が岳 から 杵島郡と名付けられた。大町には杵島炭鉱があった。炭鉱でに ぎわった頃 この町で杵島曲(きしまぶり)という菓子がうまれた。こし餡入り抹茶 落雁の包み紙の上には 「肥前国風土記」逸文の杵島曲が書いてある “あられふる 杵島が岳を さかしみと くさとりかねて いもがてをとる “ 大町から 有明海へ広がる一帯が 杵島が岳のある 白石平野である 杵島というように ここは 昔 すぐ下に 有明海が迫った島だった 歌垣 のころは 沖積平野ができて 島 ではなく なって いたが やはり 有明海が 間近に迫っていた 現在 では 埋め立て られて ずうっーと 向こうに 海はある。 農作の 祈願 と 収穫 の 感謝 を 込め 春 秋 に は 村里の 若者は 酒を手に 琴を抱いて手取りあって山に登った 歌垣は 満月の日 天の神への祈りが おわると 円陣を組んで 歌をかけ合う 気に入った女を みつけ 男は 唱いかける 「あなたの赤い腰の紐 私に解かせておくれ」 歌かけられて 「あなたのその手で 私の心も ほどいておくれ」女も返す かけ合いのなかで 互いに気に入った 男と女は 闇のなかで 抱き 合った。 着物は 野で抱き合うのに 都合がよかった。いつもひとりで抱えて いる 冷たい手のひら ひとりで抱えるには重すぎるその手のひらを 互いの袖のなかへ 背衣(せごろも)のなかの やわらかな温もり い のちのおもたさの支え合えに 紐解き合えば すぐに 肌も重ね合え た 腰紐を解くと 着物は しとねに よい 長さになる。 月の色に とけ合う よろこび いのち ある こと の 感謝 満 月にさわぐ血は 歌垣の なごりなのだろうか。杵島曲 は 杵島独 特 の 曲節 で 詠われた。 《あられ降る 杵島が岳が 険しいので 草を掴んで 登ろうとして 草を掴みそこねて 彼女の手を 掴んでしまったよ》 歌垣 は 天の神 に 豊作を 祈願して 平野 を 望国(くにみ)した 後 に おこなわれる そこで 歌垣のおこなわれる場所は 平野部が見 渡せる山で 男岳 と 女岳の 両峰を もち 数十人の若者が集ま れる 平らな所だった。 古代中国の 江南省でおこなわれていた 歌垣が この 杵島が岳 で も おこなわれて い た。 中国 や タイ など の 東南アジア北部 で いま も 続け ら れ て い る 歌垣 で この 山 も にぎわった。 しとねの 女たちの 上で 玉振りみだし 豊作を 願った 男たち の 歌 が 玉ねぎ 畑 の うえ を びゅーあー と 吹き わた る。 |
| 戻る |
| あとがき 二十二歳の春、一丸章氏が講師の西日本文化サークル現代詩講座に行き始めて三十七年になる。現代詩講座は二年でやめたが、すぐに熊本の「詩と真実」の同人になった。 選者が吉野弘・川崎洋・荒川洋治各氏だったときに現代詩手帖に、丸山豊氏だったときに西日本新聞に投稿した。 野口体操とシナリオを習いたくて、福岡県筑後市にある大谷短大の演劇科に聴講生として通ったり、小説講座に結婚してからも通い続けた。詩も書き続けていた。十六年前、佐賀大学農学部大学院の修士課程を卒業後、短大で食品加工学を教えた。牛乳や生クリームを攪拌(チャーニング)すると、乳脂肪の膜が削げて乳脂肪同士がくっ付き、バターになる。学生にバターの出来方を説明している時も、実習でバターを作っている時も、私たち夫婦が見えてきた。 互いの価値観をぶつけ合い、傷つき合い、それでも自分がどう生きるのかを探し続け、ふたりを隔てる膜も無くなった時に人と人としてくっ付き、保存性のよいバターと同じくらいに、壊れにくい夫婦になれたような気がした。 バターができる過程をみていると、傷つけ合いながら固い絆で結ばれていく夫婦の出来方をみるようだった。 ちょっと違うだけで牛乳がバターになり、夫婦も互いが自分を出しきれた時に膜も必要でなくなり、バターになる。こんなことが面白くて、詩にしてみた。 二年間、九州大学へ研究生として通った研究室では、納豆のねばねばから絹のような糸や生分解しやすいポリマー(高分子吸収体)をつくり水を染み込ませて、沙漠を緑化しようとしていた。旨いL型のグルタミン酸と、旨くはないが糸やポリマーになるD型のグルタミン酸のことが、私とつれあいと姑の関係にみえた。旨いL型のグルタミン酸に、いつもくっ付いているD型のグルタミン酸で姑が熱を出したといってはヘルパーさんに呼ばれた。病院に連れて行った夕方には、肺炎になり救急車で入院。怪我したといってまた、呼ばれて入院。点滴の針を付けたままでもベットから立ち上がるので、いつも誰かが傍にいなくてはいけない。そんななかで、私の心も旨みを深くするL型のグルタミン酸から、強い繊維にもなるD型のグルタミン酸に心の構造が変わっていくような気がした。 圧搾法と抽出法の油の違いをみていたら、つれあいの山での暮らしと町での学校生活がみえてきた。ポテトチップスをみても、たくあんをみても、私の人生がみえた。ちょっと違うだけで違ってくる人生がみえた。
二○○五年より「沙漠」同人。二○○八年より「九州文学」同人。 十年間、「はてなの会」に参加している。詩人の野田寿子氏宅に毎月二十人程が集まり、自作の詩の朗読や合評をしている。
出版にあたりご尽力を賜りました方々にお礼を申しあげます。 わたしのはじめての詩集をみていただきましたおひとりおひとりに感謝申しあげます。 ニ00八年十一月 宍戸節子 |
| 著者略歴 宍戸節子(ししどせつこ) 1949年 佐賀県生まれ 「沙漠」同人 「九州文学」同人 「はてなの会」会員 「福岡県詩人会」会員 818-0103 太宰府市朱雀3-8-5 ℡ 092-925-4410 発行日 2008年12月25日 発行所 土曜美術社出版販売 東京都新宿区東五軒町3-10 |
| 戻る |